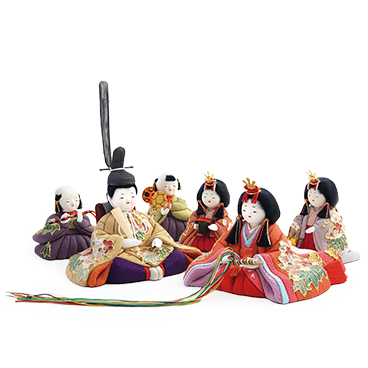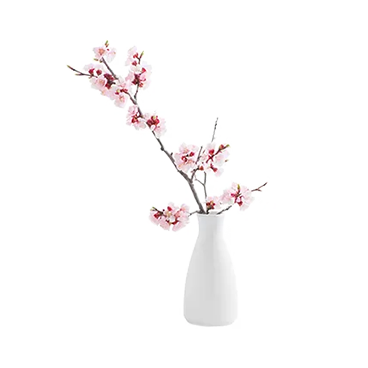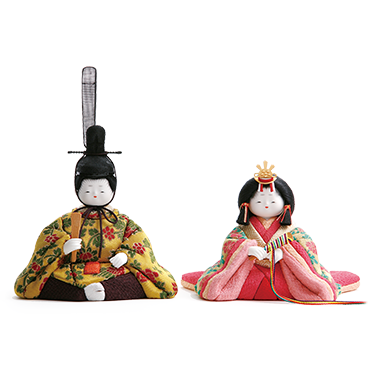お雛さまをご検討中の方へ
お雛さま選びは、
すぐに答えが出るものではないかもしれません。
何度も写真を見て、
迷いながら考える時間も、
きっと大切なひとときなのだと思います。
実際に、多くの方が何度も写真をご覧になり、
迷いながらお雛さまを選ばれています。
■ 実物をご覧になれずに選ばれる方へ
様々な理由で、
実物をご覧になれずに
お雛さまを選ばれる方も多くいらっしゃいます。
写真だけで決めてよいのか、
不安に感じられるのは自然なことです。
それでも、
何度も写真を見比べながら、
時間をかけて選ばれる方がほとんどです。
■ はじめて五色で選ばれる方の決め手
ご購入された多くのお客様が、
「自分の子にお顔が似ていると感じたことが決め手でした」
とおっしゃいます。
理由をはっきり言葉にできなくても、
どこか重なるものを感じたときに、
自然と気持ちが決まることもあるようです。
■ 価格について
はじめて五色でお雛さまを選ばれる方は、
10万円〜15万円ほどの価格帯を
選ばれることが多いようです。
高い・安いということよりも、
お顔立ちや佇まいを見て、
「これだ」と感じられるかどうかを
大切にされている方がほとんどです。
■ 長く大切にするということ
また、長く大切にできることや、
お修理のご相談ができる点も
安心だとおっしゃる方が多くいらっしゃいます。
毎年飾るものだからこそ、
この先も相談できる場所があることを
大切にされているのだと思います。
■ 最後に
迷われたときは、
お子さまがお生まれになった奇跡を
毎年そっと思い出せるような、
そんなお雛さまを見つけてください。
どうぞ、ゆっくりご検討ください。